落合集落展望所からの眺め。「わー、すごい!」とか、「へぇー、きれい」とか、多くの人が感動して眺めてくれます。
が、それだけだと5分もすれば観る所がなくなります。「早いかな?」と思いながらも「次、行こか」。 誰かが切り出します。 「せっかく来たのに。。。」と思いながら抗う根拠が見当たらず、後ろ髪をひかれながら皆さん落合集落展望所を後にします。 そんな風に見える光景によく出くわします。
「勿体ない」と思います。「いきなり話しかけて説明したい」。そんな衝動にも駆られます。
そこで、落合集落の眺め方をシリーズで紹介していくことにしました。
まずは集落のでき方です。観光サイト欄でも紹介しましたが、落合集落は上から形成されています。
落合集落の右上に山が見えます。その山と集落の間に町へ続く峠があります。四国最大の水量を誇る吉野川に繋がります。人はここを越えてやって来たと思われます。そして、その峠は落合峠と呼ばれ、町との往来に使われるようになりました。

吉野川から落合地区に到達した最初の人は眼下に広がる(?)祖谷川を見て「ここ、いいんじゃない?」と思ったに違いありません。
祖谷川は吉野川最大の支流。また落合集落は30度ほどでコンスタントに傾斜しており、断崖絶壁はありません。おまけに祖谷では珍しく一日中陽が当たる大変日射条件のよい所です。
険しい山をいくつも越えてここまでたどり着いたその人には大変条件のよい場所に見えたに違いありません。
「ここに住みたい」と思った彼らが次にやるのは水源の確保です。落合は水が豊富にある地区です。水源はすぐに見つかったに違いありません。そこでその近くにまず仮屋を作ったものと思われます。そして木を切り倒し開墾を始めます。
開墾が終われば畑を作ります。そのためにはまず土に混じった岩石を取り除く必要があります。大きな岩石は家屋の石垣に、中くらいの岩石は畑の石垣として積みます。小さい岩石は邪魔にならないように畑の周辺に投げ集めたものと思われます。こうして畑ができます。
畑と言っても痩せた土地。しかも傾斜地。雑穀しか育ちません。それでも生命を維持するには十分。荒地でも育ちやすい雑穀から栽培を始め、家と畑を交互に改善しながら、生活空間を築いていったものと思われます。
そのような営みが、集落の上から下へ下へと続いて行って、現在の景観ができあがりました。
今残っている家屋の中でも一番古いものは集落の最上部にある家です。築300年と聞いています。家の棟札にそう書かれてあるそうです。
落合集落自体は少なくとも南北朝時代(約700年前)には存在していたことが古文書からわかっています。
それよりも前のいつからここに人が住み始めたのか? それは不明ですが、東みよし町の辺りから山の尾根沿いに入って来たことは確かです。
祖谷の観光で落合集落展望所を訪れた皆さんは、グーグルマップを片手に、どういう風に吉野川から尾根づたいにここに着いたか、目の前の光景と照らし合わせながら楽しんで頂けたらと思います。


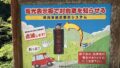
コメント